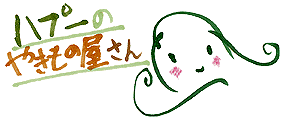 なごみのミドリ やすらぎの白 はんなりの赤 なのにとーっても丈夫♪ 1300度で焼いてるから〜♪ | クリック♪  毎月6名様にやきもの プレゼント!ハプーの 日常もここでチェック♪ | ☆技法公開や沖縄、韓国ネタは、
| |
| トップページ 作品購入 作品一覧 ご注文方法 お問い合わせ 八風窯について サイトマップ | |||
生き延びるための陶芸技法『生き陶』
★1 土揉みをしない
★2 切立ち型の品は1個挽きする
★3 ヘラは使うな
★4 指すじはダイジ
★5 3〜7ミリ気にすんな
★6 柄ごてナシ
★7 乾かしの段取り
★8 ケヅリは「輪ッか」で
★9 取っ手
★10 白化粧をダイジに
★11 穴窯には手をだすな
★12 再生するな
|
おまえたちがいつか 『生きのびるための陶芸技法』 略して『生き陶』 心して聞けぃ・・・ -------------------------------------------- -------------------------------------------- 白化粧とゆーのは品もンに白い土を掛けること やきものに使う粘土も赤い土のほーが多い ここがウチのベースやぞ タイミングが大事 乾きぎみの品もンも
うちの化粧土のベースは河東(ハドン)カオリンや そやから最近は陶器祭で売る時なんか 本体をつくって半分乾燥したトコで化粧がけ マグカップのバアイ 板にならべて口だけビニールで覆い 白化粧を勺ですくって内面にまわし掛けして 化粧をかけると なのでできるだけ早く乾燥させなきゃなんない けどマグカップなどの取っ手がついてるモンを
取っ手の重みがカップ本体に
取っ手を上にして ★ひどい「ひずみ」は売りモンにならん
やきもんの技法としては単純で 家庭の日常食器として白いものは あたたかみのある白 詫・寂の味の濃いやきもん=黒いモン/焼き〆も よっぽどの焼物好きやないと 白化粧の品もンの良さは「軽み:かろみの美」かな --------------------------- ここが八風窯のベースや おもろいぞー ネタはいっぱいころがってる 備前/伊賀/壺屋・・・ いーっぱいの魅力あるやきもんがあって そこには手つかずの無限の荒野がひろがってて 自分流にそんな仕事したら一生飽きんと ---
|
| トップページ 作品購入 作品一覧 ご注文方法 お問い合わせ 八風窯について サイトマップ |
|
Copyright(C) 2000-2006 happuyo. All Rights Reserved.
|


