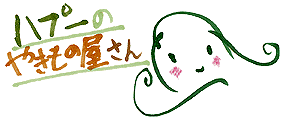 なごみのミドリ やすらぎの白 はんなりの赤 なのにとーっても丈夫♪ 1300度で焼いてるから〜♪ | クリック♪  毎月6名様にやきもの プレゼント!ハプーの 日常もここでチェック♪ | ☆技法公開や沖縄、韓国ネタは、
| |
| トップページ 作品購入 作品一覧 ご注文方法 お問い合わせ 八風窯について サイトマップ | |||
生き延びるための陶芸技法『生き陶』
★1 土揉みをしない
★2 切立ち型の品は1個挽きする
★3 ヘラは使うな
★4 指すじはダイジ
★5 3〜7ミリ気にすんな
★6 柄ごてナシ
★7 乾かしの段取り
★8 ケヅリは「輪ッか」で
★9 取っ手
★10 白化粧をダイジに
★11 穴窯には手をだすな
★12 再生するな
|
上が カンナ 下が 輪ッか カンナで削ると刃を磨がんなんやろ←時間ムダ 京都のロクロ師が水挽きをまとめてやって品もン養生 益子でおぼえてきたんやけど「輪ッか」 これは強力な武器 カンナのケヅリごろより ケズリのタイミングが さらーに 削りの「表情」がつけやすい さ 実際↓
カンナは背側をつかう 刃はいらん 輪ッかケヅリでケヅリごろの品は やわらかい品の底を一気に幅広く削るには 高さがでたら
輪ッか で 高台の直径を決め
輪ッか で 高台の内側を削る オサカナの形の3辺のカーブを
表情のある 仕事してある 光と影が きっぱりと交わって 水挽きでつけた指筋も 「風」 うちの屋号は八風窯(はっぷうよう)やからね -------------------------- 口つくり 口から1センチと こーゆー作りをしておけば 手取りが軽く 割れにくい品 になる ----------------- ふだん使いの生活の道具としての強度を ここ↑がこれからの時代に ----- 適度な「持ち重り」は陶器の持ち味 ざっくりした/素朴な/あたたかみのある/ そんな「美」のやどった品を 作れ! ------------------------------------------ いやー つい力はいってしまいましたぁ〜♪ ---
|
| トップページ 作品購入 作品一覧 ご注文方法 お問い合わせ 八風窯について サイトマップ |
|
Copyright(C) 2000-2006 happuyo. All Rights Reserved.
|




